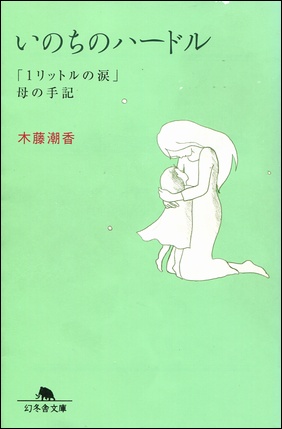紺野 キタ
紺野キタは1991年に「見えない地図」でデビューしています。彼女の作品は「1リットルの涙」以外は読んだことがありません。この作品で見る限り,すっきりした絵柄は割と好みですが,活躍の場が同人誌や「Webスピカ」などですから,これからも私との接点はおそらくないでしょう。
「1リットルの涙」は「木藤亜也」さんが発病した15歳(中学3年生)からボールペンで文字を書けなくなった21歳までの日記をそのまま本にしたものであり,コミカライズ作品は中学3年生から高校1年生の時期を描いています。
主人公の「木藤亜也」は原作と同じですが,その他の登場人物の名前は微妙に変えてあります。また,高校時代の同級生の石川君や3年生の井上さんはコミカライズしたときの物語性を高めるためのものであり,原作にはそれに相当する人物は出てきません。
難病と向き合う少女の姿やその思いは原作の「1リットルの涙」により強く表現されています。また,母親である潮香さんがどのようにして亜也さんを支えてあげたか,難病を抱える娘とともに生きていく上でどのような問題に直面したかについては「いのちのハードル」に記されています。
やはり,この2冊を読まなければ難病を抱えた患者やその家族の思い,障害者を見る社会的な視点が見えてきません。特に「いのちのハードル」の中には母親の立場から高校の担任,入院先の医師,入院中の付添い家政婦に対して批判的な見解が記されている箇所があります。
そのような批判は障害をもった方やその家族にとっては当然のものですが,批判された方々はその時代の社会においては平均的な水準であろうと推測します。
「ノーマライゼーション」という言葉が社会的に認知されるようになったのは比較的最近のことであり,亜也さんの時代には障害者を社会から隔離する方向が主流でした。
それに対して「障害者を排除するのではなく,障害を持っていても健常者と均等に当たり前に生活できるような社会こそがノーマルな社会である」という考え方が「ノーマライゼーション」です。
言葉で説明するのは簡単ですが,実際にそのような社会を実現するためには多くの障壁があるのも事実です。「1リットルの涙」と「いのちのハードル」から福祉や医療のありようを考えてみたいと思います。
「1リットルの涙」の出版
「1リットルの涙」は中学3年生の時に治療法のない難病である「脊髄小脳変性症」を発症した「木藤亜也」さんが綴った日記を本にしたものです。
「脊髄小脳変性症」とは小脳・脳幹・脊髄の運動に関連する神経細胞が徐々に変化し消失していく病気です。日本における発症率は10万人あたり5-10人であり,約3割が遺伝性,7割が非遺伝性(孤発性)とされています。
この病気の特徴は神経細胞のうち運動に関連するものだけに選択的に発生すること,および個人差はあるものの10年,20年という長い期間をかけてゆっくりと進行することです。身体能力は徐々に失われていく反面,精神活動には影響がありません。
「木藤亜也」さんの場合は15歳で発症し,25歳のときに亡くなっていますので,この病気の中では速い進行ということができます。
母親の潮香さんは保健婦をしており,長女の亜也さんの歩行時の揺れ,転倒した時の状況,痛みのない症状などから筋肉か神経の病気を疑い,名古屋大学附属病院で診察を受けさせます。
診断は「脊髄小脳変性症」であり,運動神経が徐々に消失していき,数年後には寝たきりになり,呼吸不全を起こすなど予後は不良であること,治癒した例は皆無であることを知らされます。
このとき亜也さんは15歳であり,この診断は潮香さんにとっては娘に対する緩慢な死刑宣告のようなものであったことだと推測します。進行性の病気ですからいずれ亜也さんに真実を話さなければならない時期が来ます。
潮香さんは事実を話す前に娘が病気に向き合う強さをもつようになるにはどうすればよいかと心を砕きます。その一つの形が日記でした。亜也さんは文章を書くことが好きでしたので,先生に病状を正確に伝えることを目的に日記を書くことを提案し,亜也さんは自分の病状や自分の感情,周囲の人々とのやりとりなどを記すようになります。
病状が進行し,主治医から自分の病気について知らされたのは亜也さんが18歳のときでした。母親や家族の支えもあり,その頃には亜也さんは病気に負けない心を培っていました。
「脊髄小脳変性症」は歩行のように大きな動作だけではなく,言葉を発音する,文字を書くといった小さな動作にも影響を与えるようになります。また,呼吸,咀しゃくのように普段,私たちがまったく意識しないで行っている生命維持動作まで困難にします。
亜也さんが言葉の多くを失ったのは20歳頃であり,文字を書けなくなったのは21歳のときです。家族との会話は文字盤を使用するようになりますが,文字盤に手を触れる動作も次第に困難になります。
「1リットルの涙」は母親の潮香さんが亜也さんの日記の一部をそのまま原稿にしたものです。その頃,亜也さんは肺炎を起こしており,命の危険性を医師から告げられていました。
原稿作成→出版は時間との闘いでした。幸い肺炎の危機は脱することができ,亜也さんは母親と共同でゲラ刷りをチェックすることができました。本が完成したのは昭和61年(1986年)のことであり,亜也さんは23歳になっていました。
自分の思いが活字になった本を手に取り,亜也さんは感激のため(すでに言葉は失われていたので声にはなりませんでしたが)大粒の涙を流していました。
20歳の頃には付き添いが必要な入院となり,不自由な手にフェルトペンを握って母親に「私は何のために生きているんだろう」と伝えた亜也さんが,次第に進行していく障害を抱えた自分の思いや懸命に生きた証を社会に向かって発信することができた至福の瞬間でした。
潮香さんは亜也さんの希望によりその本を十数日かけて読んであげました。「1リットルの涙」は社会的に大きな反響を呼び,多くの人々から暖かい励ましや自分も強く生きたいという読者の声が亜也さんのもとに届けられました。
しかし,その間も病状は進行していき,ついに食べることができなくなります。現代医学では鼻孔からのチューブで栄養を摂ることはできますが,亜也さんはそれを拒否します。
点滴だけでは生命を維持することはできませんので,容態は次第に悪化し,自発呼吸が停止し,家族に見守られながら亜也さんは旅立ちます。それは発症から10年後の25歳のことでした。
障害者を見る視点(教師)
中学3年生のときに病気を発症した亜也さんは普通高校を受験し,合格します。当時の学校には「バリアフリー」などという概念はなく,通常の身体能力を有する生徒を基準に造られています。
亜也さんの病気でもっとも影響の大きなものは歩行です。私たちは歩けることなどは当たり前のことだと考えますが,歩くという行為はたくさんの筋肉がバランスをとりながら動くことにより達成できるものです。
私たちは意識しないでもそのような複雑な筋肉の動きを実現することができます。それは,乳児の頃から体が時間をかけて習得したプログラムであり,そのプログラムを実行するのが小脳です。この小脳が働くことにより私たちは(意識しないでも)多くの動作を滑らかに行うことができます。
亜也さんの病気である「脊髄小脳変性症」は小脳の働きが失われていきますので,すべての動作が少しずつスムーズにできなくなります。そのもっとも顕著な運動が歩行です。
校舎内の移動は亜也さんにとっては苦労の多いものであり,級友の助けなしでは難しいものです。また,咀しゃくにも時間がかかりますので昼休み時間だけでは足りません。トイレに行く回数を減らすため水分の摂取も抑えなければなりません。
亜也さんの通った普通高校は亜也さんの病状の進行によりこれ以上はここでは無理という決断を下します。そのときの理由として「級友たちが亜也さんのサポートに疲れている」ことをあげています。
しかも,担任はそのことを亜也さんではなく母親に告げています。担任にしてみれば本人にそのことを直接話すには忍びないということなのでしょうか。どうせ決定するのは両親なのだから,母親に話せば大人の会話で済ませられるということなのでしょうか。
その当時の社会風潮からすると一概に責められることではありませんが,障害をもった生徒と向き合う姿勢に欠けています。
普通高校から養護学校に転校することは自分が障害者であることをいやでも思い知らされることになります。担任はそれが亜也さんにとってはとてもつらいことだということに思いが至らないようです。
学校と本人の努力により可能な限り普通高校で学び,どちらかの条件が無理になったら別の選択をしなければならないと説明すれば,亜也さんは自らの意志で養護学校行きを選択することができたはずです。
同じように転校するにしてもどうすれば生徒の心の負担が軽くなるかを考えなければなりません。それができていれば亜也さんは転校の決断の前に「1リットルの涙」を必要としなかったかもしれません。亜也さんは2年生から養護学校に移ることになりますが,日記には次のように記されています。
先生はなぜ直接,わたしと話し合ってくれなかったのですか。今日も明日も繰り返す難儀な生活だけど,わたしが気持ちよく去ることができるよう,なぜ,先生はわたしの話を聞いてくれなかったのですか。もし,そうして下さっていれば,二年生から転校しますと素直に言えたのに・・・・・・。
人のこころを傷つけるのは簡単ですが,ほんのわずかな思いやりや注意でそれをずっと軽減させることができます。弱い立場にいる人はそうでない人に比べると心の傷を受けやすいということを忘れないようにしたいものです。しかし,1970年代末の学校の状況を考えると,(悲しいことですが)私はこの一件で亜也さんの担当教師を責める気にはなりません。
障害者を見る視点(医師)
養護学校を卒業し,しばらく自宅で療養していた亜也さんは病気の進行により入院することになります。この時期になると医療行為としても硬直,嚥下障害,痰の喀出困難など応急処置が必要なことも度々起きるようになっています。
また,生活全般をサポートしてくれる家政婦が必要な状況になっています。家政婦とは24時間付きっ切りで入院患者の身の回りの世話をする人ですが,亜也さんのように生活全般に手間がかかる患者は敬遠される傾向にあります。
主治医は現在の家政婦ができるだけ長く続けられるよう母親の潮香さんに「仕事を止めることはできないんですか」とたずねます。おそらくこの医師は潮香さんが仕事を止めて月の半分くらいを付添いとして詰められないのか,そうすれば家政婦の負担が軽くなるので長く続けてもらえると言いたかったのでしょう。
他人の家庭の中に土足で入り込んでくるようなこの発言に潮香さんは激怒し,転院を即断します。それに対して主治医(実際にはほとんど亜也さんを見ることはありませんでした)は自分をさしおいてそのようなことは許されないと語りますが,潮香さんは次のように話します。
弱い立場にある患者と家族のことを考えず,よく確かめもせず平気でそんなことをいう医師なんて,医療の場で働く医師とは思いません。亜也の主治医とも思いません。主治医と相談して今後のことを決めますからかかわってくれなくて結構です。最後に一言,もう少し医療に携わる医師として勉強することがあると自覚して下さい。
いや~,潮香さんはよく言いましたね。彼女の言う通り患者とその家族は病院や医師に対して弱い立場にあります。その状況を背景に「お母さん,仕事を止められませんか」とたずねる神経には医師である以前に人間性に問題があるように感じます。
現在では「患者に寄り添う医療」が当たり前のように語られていますが,当時の医療現場では「世話をしてやっている」という感覚が普通でした。亜也さんの自称「主治医」も患者の世話をする家政婦のことで面倒はごめんだということなのでしょう。現在のネット社会では人権問題として厳しく糾弾されるような話がまかり通っており,患者とその家族は耐えるしかなかった時代なのです。
障害者を見る視点(家政婦)
入院時の家政婦も潮香さんにとっては悩みの種でした。亜也さんは自分に厳しくわがままなどは言わない性格でしたが,重度の障害により食べる,排泄する,着替えるなど生活のすべての面で人の手を借りなければならない状況でしたので,亜也さんの世話は家政婦には大きな負担となっていました。
そのため,家政婦が長続きせず,亜也さんも家政婦さんに辞められたらどうなるんだろうという恐怖があり,人によっては我慢を強いられる入院生活を送ることになります。
中には亜也さんが食べるの遅いと食事を量ではなく時間で切ってしまうような人もいました。彼女は本人を前にして頭が正常だと考えているのは親だけだ,口をもぐもぐしているばかりでさっさと食べられないのかなどと放言しています。
同じ病室の患者からこの話を聞いた潮香さんの心は怒りに震えます。亜也さんの病室で「お母さんにいいたいことがあるでしょう。がまんしなくてもいいからいってごらん」と告げると亜也さんは大粒の涙を流します。その涙がすべてを物語っています。
この家政婦さんの非人間性は相当なものであり,潮香さんの立場からすると「鬼」にも感じられたことでしょう。このような家政婦は人格に問題があり,楽な患者に付いても同じような不平・不満を患者にぶつけることでしょう。
人格に問題がある人間は強い立場にあるとどうしても弱者に横柄な態度をとるようになります。これは人間の感情の中でもっとも卑しいものの一つであり,そのような人たちは他人の痛みに気が付かないあるいは気付こうとしない人たちです。
表面的にはやさしい人を装うことはできても,状況が変化すると人格の欠陥が現れてきます。家政婦探しで家族に迷惑をかけたくないと考える亜也さんはこのような家政婦にさえ我慢を強いられるつらい場面もありました。
逆に亜也さんに寄り添ってくれる家政婦に出会ことができたときは病気の辛さも半減したことでしょう。人生の最後の6か月間はこのような人間味にあふれる家政婦に世話してもらい,幸せな時間を過ごすことができました。
現在は身体介護,生活介護は介護施設の仕事となっています。私の母もそのような施設におり,着替え,排泄,洗面なども介助が必要な状態であり,職員の暖かい対応には頭が下がる思いです。
亜也さんの家政婦の時代に比べてはるかに要介護者に寄り添う姿勢は社会が30年かけて育てたものだという気が強くします。しかし,それは平均的な水準が上がったということであり,現在でも介護施設における要介護者や障害者に対する虐待はしばしばニュースになっています。