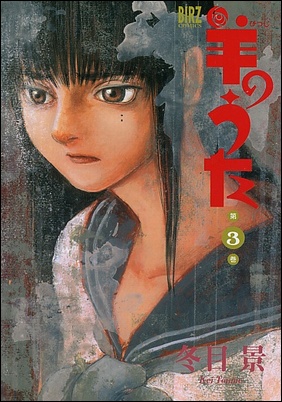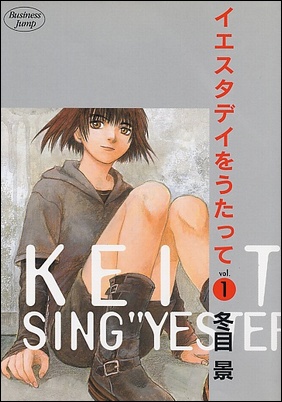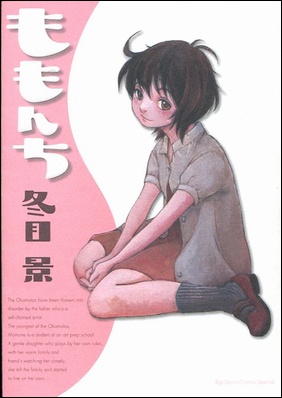90年代からマンガが変わってきました
久しぶりに単行本を集めてみようかなと思う作家に巡り合うことができました。我が家の書棚に溢れる本に対して何らかの総量規制をかけなければならない事態になってから15年くらいが経ちました。その間,ことマンガに関してはほとんど新しいものの収集はありませんでした。
1980年代の半ばから子どもたち用のマンガは,キャラクターの人気に依存した「眺める」ものに変質してゆき,この世代が成長した1990年代の半ば頃からは青年誌もその傾向に染まっていったように感じます
そのため,最近のマンガに嫌気がさしていたことも新しいコレクションが増えない要因にもなっていました。冬目さんの作品はそんな私にも十分「読める」内容でした。
物語自体は単純なものですが,ヒロインの千砂の屈折した心理状態,およびそれを示唆する夢や記憶のフラッシュバックの描写が時系列に関係なく挿入されているため,2回読んでようやく理解できました。吸血,近親相姦という恐ろしく暗いテーマを哀しく,美しい物語に仕上げた冬目さんの力量を感じる作品です。
聖少女との対比
物語のキーワードを並べてみると,「血」,「記憶」,「父と娘の愛」,「姉と弟の愛」,「一砂と葉の愛」,「千砂に対する水無瀬の愛」ということになります。私はこのうち「血」,「記憶」,「父と娘の愛」,「姉と弟の愛」という4つのキーワードから「聖少女」という小説を連想しました。
「聖少女」は1965年に発表されたもので,そのとき作者の倉橋由美子さんは30歳でした。2005年に彼女が亡くなったので,その追悼出版が相次いでいます。そのためネットの本屋に次のような「聖少女」の解説を見つけることができました。
自動車事故で記憶喪失におちいった未紀のノートにしるされた過去,「パパ」を異性として恋した少女の崇高なまでに妖しい禁じられた愛の陶酔を強烈なイメージで描いて,特異な小説世界をくりひろげる。未紀と青年Kとの愛、未紀と「パパ」との愛,Kとその姉Lとの愛,三つの愛の錯綜した展開のなかに,不可能な愛である近親相姦を選ばれた愛に聖化しようと試みた作品。
未紀のノートは「いま,血を流しているところなのよ,パパ」というショッキングな文章で始まっています。この小説は30年くらい前に読んだきりなので内容はもうほとんど記憶に残っていません。
書棚を探してみたのですがすでに処分してしまったようなので,それほど私の感性に合致したものではなかったようです。もっとも現在,読み直すとまた違ったものになるかもしれません。
解説にもあるように「不可能な愛である近親相姦を選ばれた愛に聖化しようとした試み」は「羊のうた」にもそのまま適用できると考えます。そのような聖化の試み対して,読者が嫌悪感無しに入っていけるための仕掛けが「高城家の血」となっています。
人類の二大タブー
「羊のうた」は近親相姦と並んで人類の二大タブーとなっている「親殺し」にも言及しています。実の父親を精神的に追い詰めて自殺させたと考えている千砂には,意識の底に封印された記憶がありました。
記憶の封印が破れ,今まで自殺したと信じていた(信じ込まされていた)母親の死が,自分に起因するものであることが分かった時,彼女の受けた衝撃の大きさは察して余りあります。
「千砂は・・・生まれて来ちゃいけなかったの?」という幼い頃の疑問に自分なりに答えを出した千砂は,生きることに対する執着心を捨ててしまいます。
この作品のおもしろさは千砂の屈折した心理をどう読み解くかという一種の謎解きにあると考えます。作者の冬目さんは心理描写が非常に巧みであるという評価が確立しているようです。
確かに会話の中の言葉の端々に,四角で囲まれた独白の中に登場人物の心理が的確に描写されています。同時にネームの無いこまの中で展開される人物の表情,あるいはモノに活字にしていないこころの動きが託されています。そこをしっかり看ていくと物語の深みが伝わってきます。
一砂や葉のこころは割とストレートに表現されていますので,活字だけでもほとんど理解することができます。しかし,千砂のこころだけは活字化されていない部分に多くの内容が込められています。
これを理解するためには何回か読み直さなければなりません。ネット上の書評に「読み直すたびに新しい発見がある」という記述がありましたが,それはこのような心理描写のテクニックによるものなのかもしれません。
一砂16才,千砂17才のときから物語が始まります
物語は高城一砂が高校一年生の夏休みを直前に控えた頃から始まります。初出が1996年なのでその時間を基準に過去を振り返ると次のようになります。
1979年:千砂誕生
1980年:一砂誕生,この後で百子が発病
1982年:千砂が3才で発病
1983年:百子死亡,3才の一砂が江田家に預けられる
198X年:志砂と千砂は横浜に引っ越す
1986年:千砂が水無瀬に傷を負わせる
1993年:中学生の千砂に水無瀬が父親から離れるべきだと助言する
1995年:志砂が自殺,千砂も自殺を図るが水無瀬に止められる
1996年:千砂は東京の高城家に一人で住むようになる
1996年:一砂16才,千砂17才のときから物語が始まる
美術部室で赤く染まった絵と八重樫葉の傷をみた一砂は不思議な感覚にとらわれ,ソファーで横になります。高城の血に引かれるように一砂は子どもの頃,家族で住んでいた家を訪ね,江田家に引き取られてから会ったことの無い姉の千砂に再会します。
半年前に父親志砂を自殺で失った千砂は,父親の死および衝動的に血を吸いたくなる高城家の奇病について一砂に話します。この血の衝動は吸血鬼のように生理的に血が必要ということではなく,精神的な渇きを感じるというもので,誰の血でもよいというわけにはいかない性質のものです。
美術部室で三度目の発作に見舞われた一砂は,人気の無い川原で頭を抱え,発作を抑える薬を飲むことに躊躇します。そこに千砂が現れ,自分の腕を傷つけ,「こっちに来て」と一砂に告げます。それは父親に似た一砂を普通の世界から自分の世界に誘なうためのものでした。
血を舐める一砂を見る千砂の表情はとてもやさしく,「父さんがあたしを必要としてくれてたから…こんなくだらない人生でもここまで生きてこられた」と自分に言い聞かせるように話します。
物心がついたときから,普通の社会生活を意味する「羊の群れ」には入れないことを自覚せざるを得なかった千砂は,壊れてしまった父親との世界が復活するかもしれないという期待を抱いており,それが彼女の慈母のような表情となって表れています。
三歳で発病し,父親の血無しには生きてこれなかった千砂にとっては,父親との暮らしが自分の世界の全ててでした。学校を含む外の世界は,自分が他の人とは違う,自分はこちらの世界にはいてはいけないと認識するところでした。
しかし,父親の志砂にとって千砂は妻百子の身代わりでに過ぎなかったのです。もちろん,親として不憫な娘を溺愛する一面はあったかもしれませんが,その向こうにいつも妻の面影を求めていました。
彼のこころは,千砂がそれに気がつく年齢に達したとき罪悪感と恐怖感に満たされたことでしょう。実際,千砂は「父親を自分のものにしたかった」と話しています。
妻を裏切るという罪悪感,妻の身代わり人形にしてきた娘が,妻ではない自分への愛を求めるようになった恐怖感に耐えられなくなった志砂は,娘を道連れに死のうとしますが,果たせず自殺します。
残された千砂は生きる目的を失い,後追い自殺をしようとして水無瀬に止められます。父親の呪縛が余りにも強かったため,千砂は水無瀬の血を飲むことができません。
しかし,血を求める発作は確実に起きるため,水無瀬は強い向精神薬を処方します。それは,生まれつき心臓機能の弱い千砂にとっては負担の重い薬でした。一砂に再会した頃,彼女の心臓はかなり悪化していたようです。
一砂の葛藤
一砂は美術室で四度目の発作に襲われます。千砂からもらった薬も彼には効果がありません。そのとき入ってきた八重樫葉に一砂は自分の病気を告白し近づかないように警告します。
好意を寄せる人だから自分から遠ざけなければならいない,相手がいい人たちだから巻き込みたくない,一砂の苦悩はいくつかの場面で描かれています。
クラスメートの木ノ下との会話,江田のおばさんとの会話の中で,彼を大事に思う暖かい人たちとの関係を断ち切るため,こころにも無いことを言わなければなりません。このあたりの描写も読み応えがあります。
一砂は高城の家に行き,指からしたたる千砂の血を舐めます。血が畳に落ちる時の「パタ」という音が生々しく聞こえます。千砂は「あなたを癒すことのできるのはあたししかいないのよ」と告げます。
「こんな自分に耐えられない」とつぶやく一砂に対して千砂は「あたしではだめ,あたしはあなたの生きる理由にはならない?あたしはあなたが必要だわ」と告げます。これは彼女なりの婉曲的な告白なのでしょう。千砂はさらに高城の家で一緒に暮らすことを提案します。
高城の家から戻る一砂を葉が駅で待っています。彼女は「何を聞いても平気だよ・・・だってあたし好きなんだもん,高城くん」と告白され,「病気の事…詳しく聞かせて」と問い詰められます。
しかし,葉の側にいると一砂はやはり発作に襲われます。葉は自分の指を切って一砂の前に出し,「こうすれば高城くんの側に居ていいんでしょう」と迫ります。
一砂は葉の血で自分の渇きが癒されることを本能的に知っています。しかし,好意を寄せる人を傷つけて自分の渇きを癒すことは,一砂の理性が許しません。このときの両者の表情の移り変わりは,心理状態をみごとに絵だけで表現しています。渇きと抑制の葛藤のあまり一砂は気を失い,水無瀬の勤務する病院に運び込まれます。
病室で一砂,千砂,葉,江田夫妻が顔をそろえ,千砂は高城の家で一緒に暮らすことを宣言します。一砂のベッドに腰を下ろした千砂は葉が二人の関係において,大きな障害要因になることを直感したようです。千砂は「これからは二人で生きていくのよ。あたしがあなたを護ってあげるわ」と切なさのこもった眼差しで一砂に語りかけます。
しかし,帰宅してから千砂は水無瀬に「君が一砂くんに父親を重ねている事は知っている。あの事をまた繰り返すつもりなら,僕は黙っているわけにはいかない」とクギをさされます。
水無瀬はさらに「君が…一砂くんにとって必要な存在でありたいように,僕も君にとってそうでありたい」と続けます。父親を亡くした後も千砂は水無瀬の愛に応えようとはしませんでした。彼女にとっては水無瀬はやはり外の世界の人間だったのかもしれません。
父親の呪縛
退院した一砂は高城の家に住むようになります。千砂を刺す夢でうなされる一砂をやさしく抱いた千砂は「私が怖い?」とたずねます。そして自分が父親に殺されかけたことを告白します。それに対して一砂は「僕を助ける気になったのは,やっぱり父さんに似ているから」と問いかけられ,「そうかもしれない…」とつぶやきます。
この時点では千砂はまだ父親の面影をもつ一砂の側に居たいという感情だけに支配されているようです。父親との二人だけの生活は「異常な家庭,奇妙な感情」と理解してはいてもそこは彼女の世界の全てでした。
血の渇きと妻への渇望という利害関係の一致は二重螺旋のように千砂のこころを呪縛しています。自分だけを置き去りにして逝ってしまった父親を憎むことでこの呪縛から逃げようとした千砂は,同じ高城の病に悩む一砂に出会い,それから半年の間に大きな感情の変化が生まれます。
千砂のこころの変化
この変化のターニング・ポイントになったのが第24話です。夏休み明けの新学期に川原で千砂は葉に出会い,一砂の病気を知ってなお彼の力になりたいと言う葉に対して一砂に会わないように求めます。
こころの中では葉も同じように一砂を癒せることは知っているにもかかわらず,「一砂を癒せるのは,同じ苦しみをもった私だけよ。そして,あの子を護れるのも・・ね・・・」と千砂は宣言します。
そのときの表情の中にあるものは明らかに嫉妬です。「一砂を護る」という言葉に込められた思いは「二人だけの世界を護る」ということなのでしょう。
その夜,千砂は激しい胸の痛みに苦しみます。それに気づいて部屋に入った一砂に「お願い,私を必要として」,「生きるための手段でもいいから・・・私の傍にいて・・・もうわたしを独りにしないで」と告げます。千砂は葉と会ったときのことを話しながら,嫉妬にかられ一砂に口付けます。
しかし,すぐに「あなたをこの血で縛っても心まで縛ることはできない・・・そんなことは分かっている」,「人形でもいい。母さんの身代わりでもいいから・・・ただ・・・父さんに側に居てほしかった」という理性と感情が入り混じった気持ちを吐き出します。
それに対して一砂は「俺がずっと側に居るよ」と言います。千砂を真正面に見据えたこの言葉により,千砂のこころは父親の呪縛から解き放たれたのです。
そして死ぬ間際に「あなたを弟でもなく・・・父さんの代わりにでもなく愛したわ,・・本当よ・・・命をかけて」と言い切れるまでになりました。
一砂には父親と同じことはさせたくない,だから一砂の血は吸わないという千砂の強い思いは,父親の呪縛から逃れるためというよりは高城家の呪われた運命と闘う意志の表れだったのでしょう。
血で縛られることなく純粋に一砂を愛することが,彼女なりの病気との闘いだったのでしょう。発作を強い薬で抑えることは心臓機能が十分ではない千砂にとってはまさしく命を削ることになります。
眠れないまま月を見ていて一砂は激しい発作に襲われ,思わず千砂に抱きつき首筋を噛みます。千砂は一瞬苦痛の表情を見せますが,すぐに恍惚の表情に変わります。この首筋への吸血はほとんど愛の代償行為のように描写されています。
そのとき千砂は「もっとわたしの血を求めて,わたしの血があなたの血となり骨となる」とつぶやきます。この言葉は自分の体を転換させて子どもを作り出す女性ならではの表現であり,二人の間の神聖な血の契約でもあったことでしょう。この血の契約こそが,千砂にとってもっとも確かなものとして描かれています。
葉に癒される一砂
千砂に促されて久しぶりに学校に行った一砂は,階段で転がり落ちてふたの開いた塗料の色に触発されて発作を起こします。学校内の人気の無いところで苦しむ一砂に葉が駆け寄ります。
「近寄るな」という一砂の警告に逆らい葉は一砂に抱きつきます。一砂は拒絶しようとしますが,葉の「いいよ」という声に促されるように彼女の首筋を噛み血をすすります。
一砂が本能的に感じていたように,千砂が直感的に恐れていたように葉の血で発作はおさまります。葉はこの傷が支えとなり一砂を待ち続けることができるようになります。葉の血で一砂の渇きが癒されたことは,一砂の将来に別の希望があることを示唆しています。
一つの結末
元看護婦の風見が志砂の自殺原因を調査し始めたことから,千砂は自分の記憶の底に封印されていた母親の死について思い出してしまいます。発病した千砂を道連れに死のうとしたとき,千砂は苦しさのあまり花鋏で母親を刺してしまいます。
自分が母親を殺したことを知った千砂は生への執着を失い,まっすぐに死に向かっていきます。そのような時にも「俺は父さんのようには逃げない」という一砂の言葉は,千砂の愛を純粋なものに聖化することになったことでしょう。
最後の夜に苦しむ千砂は看病する一砂に対して「わたしを見ていてね」,「あなたに会えたから,私は父さんの影から逃れることができた」,「あなたを弟でもなく・・・父さんの代わりにでもなく愛したわ・・・本当よ・・・命をかけて」と告げます。
それに対して一砂は「千砂といっしょにいたのは僕がそうしたかったからだ,僕は千砂を選んだ」と思いを伝えます。千砂は一砂の頬に手を当てながら「それ以上の言葉はないわ」と感謝の意を伝えます。
自分で「この下らない人生」と言い切った千砂のこころは,最後の瞬間に満たされたものになったのでしょう。千砂は一砂を普通の生活に,江田夫妻と葉に返そうとしますが,一砂は「ごめん,俺…良くなんてなっていないんだ」と告げ,千砂と一緒に逝くことを伝えます。
その言葉を聞いた時の千砂の切ない表情が何かを語っているように感じます。私は「分かったわ,高城の血は私たちで終わりにしましょう,私と一緒に行きましょう」と解釈しました。
翌日,胸騒ぎに襲われ高城の家に向かった水無瀬は,寄り添うように眠る二人を発見します。近くの石油ストーブに置かれたやかんが「シュン,シュン」と音を立てています。
冬目さんはこのよう情景描写にも力を入れており,モノを通して何かを語りかけてくる手法もよく使われています。古い日本式の家屋も手を抜かず,しっかり描いています。
個人的には高城家の血でつながった二人が一緒に死ぬのはある意味でこの物語の一つの必然であり,完結された美しさではあると考えます。最終話をエピローグとして,関係者による二人のこころのあり様を回顧するという展開もあったと思います。
それに対して,作者はもう一つの結末を用意しました。一砂はかろうじて命をとりとめ,この一年間の記憶を失うという設定で新しい生活を始めるようになります。記憶を失った一砂に対して八重樫葉は「ここから始めればいいのだから」と独白します。
作者は呪われた高城の血をもつ一砂にも未来の希望はあるとしたかったように感じます。しかし,この都合のよい記憶喪失という展開だけは避けてもらいたかったですね。一砂が命を取り留めるにしても千砂を失った大きな喪失感と高城の血とどのように対峙していくかを正面から描くべきだった考えます。